
自作スピーカー入門 |

| スピーカー自作は素晴らしい趣味です! | |||||||||||||||
| みなさん!スピーカー自作は素晴らしい趣味です。僕もちょっと前までは敬遠していました。学生時代、ONKYOの「MONITOR100」という高級スピーカーを使っていたので、それで満足していたからです。ところが、そのスピーカーが壊れて決心がつき、手軽なものから製作してみたところ、面白い面白い!実に生き生きとした音が出てくるではありませんか。もうメーカー製のものには戻れません!安いし、楽しいし!工夫すればするだけ、音は応えてくれます。第一この世で自分だけの物が作れるのですから!芸術は創造的なもの。ただ音楽を鑑賞する受身的な立場から、創造的に「音楽を聴く」きっかけにもなります! | |||||||||||||||
| そんなに難しくありません | |||||||||||||||
とは言え、どこから知識を得れば良いのでしょう?安心してください。日本には長岡鉄男先生という方がおられました。残念ながら2000年の初夏に亡くなられましたが、長岡先生等が書かれた図面集等は今でも書店で市販されています。長岡先生は技術者ではなくいわゆるオーディオ評論家でしたから、専門知識がない人が読んでも十分分かる内容です。それらを参考にすれば、専門知識が全くなくてもOKです。長岡先生独特の語り口についつい惹きこまれてしまい、製作してみたくなる事請け合いです。「再生という言葉が生命の復活、甦りを意味するのであれば、このD-55こそ再生機であろう」(長岡鉄男最新スピーカークラフト3 バックロードの傑作/音楽之友社)などと書かれているのですから。
まずは以下の本を購入される事をお薦めします。 スピーカーユニット等のパーツは秋葉原のショップでないと無理です。しかし、通信販売もやっていますから、以下のHPや「STEREO」誌等の広告を見て注文すれば、地方の方でも手に入れる事ができます。
何を自作するの?
|
え?スピーカーのどこを自作するの?ですって?。ごもっとも。振動する部分(ユニットといいます)は作れません(作る人もいます)。普通、「スピーカー自作」と言う時は、ユニットを取りつける箱(キャビネットとかエンクロージャーなどどいいます)を自作することをいうのです。「なあんだ」という声が聞こえてきそうです。しかし、箱はユニット以上に音質を左右するのです。「そんなばかな!」というあなた!試しにお使いのスピーカーからユニットをはずして鳴らしてみてください。見事に低音の抜けた、カシャカシャした音になるでしょう?さあ、鳴らしながら箱に取りつけてみましょう。箱に取り付けた瞬間、音は不思議なくらい生命を取り戻したでしょう?ね? | なぜ、箱が必要かというと、低音を確保するためなのです。波は周波数が高い程直進性が増し、逆に低いと波動性が増し回り込む性質があります。ですから、ユニットを裸で鳴らすと、ユニット前方から出た低音は後ろにも回りこんでいきます。逆にユニット後方から出た低音は前にも回りこみ、ユニット前方から出た音と重なります。ユニットの前にでる音波と後ろに出る音波は位相が反対ですから、重なれば互いを弱め合う事になり、低音が出なくなるのです。それを避けるために箱があるのです。つまり、ユニット後方から出た音を閉じ込めるためにあるとも言えます。 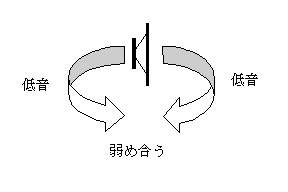
| |||||||||||||
| キャビネットの種類 | |
|
人間には20HZ~20000HZの周波数の音が聞こえているといいます。その範囲の音をまんべんなく、しかも広いダイナミック・レンジ(どれだけ正確に音の大小を再現するか)で再生するのが「良いスピーカー」の条件です。500HZ以上の音は箱がなくても再生できます。ですから、500HZ以下の低音をうまく出すために箱があるのです。キャビネットには音響学的に様々な方式があります。ただの箱ではありません。理想的な方式はなく、それぞれ長所と短所があります。 メーカー製のスピーカーは周波数レンジを広く取るためにネットワーク回路に様々な工夫がされていますが、その分ダイナミックレンジを犠牲にしているものが多いです。 一見良い音なのにオーケストラの奥行き・立体感・臨場感が感じられないのは、 ダイナミックレンジが狭いからです。 ダイナミックレンジは周波数レンジ以上に臨場感には重要なのです。 私見を言わせてもらうと、メーカーによって音の傾向は違うとはいえ、 自作スピーカーの自由度に比べれば、どれも似たり寄ったりだと思います。 自作の良いところは、メーカー製と同じ性能のものが安く製作できることではなく、 メーカー製にはない性能を持ったスピーカーが製作できることです。 音質の狙いと、ユニットの性質を良く考慮し、それにあった方式を選ぶ事が大切です。狙い通りの音が、製作したスピーカーから出てきたときの感動といったら! | |
| 平板型 :平板にただユニットを取り付け、低音の回り込みを減らす方式です。 | |
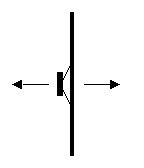
|
長所:自然な音がします。キャビネット内の空気バネ効果がなく、ユニットがほとんど負荷を受けずに動けるからです。 短所:低音を出すには、かなり大きなバッフル(ユニットを取りつける板)にする必要があります。 |
| 後面開放型 :平板型の板を一部横に回した型です。 | |
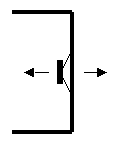
|
長所: 平板型と同じです。しかもバッフルが狭く出来るので、音場感も良いです。 短所: 低音を出すには、かなり大きなキャビネットにする必要があります。 |
| 密閉型 :文字通りキャビネットを密閉する方式です。 | |
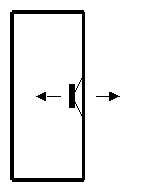
|
長所: 平板型などより小型になります。キャビネット内の空気バネの共振を利用するので低音も有利です。バスレフ型のような低音の強調感もありません。 短所: 密閉するので、空気バネ効果が大きく、ユニットが自由に動けなくなり、引っ込んだような音になります(おとなしい音として長所にもなる)。ダイナミック・レンジも小さくなります。箱の大きさも限定されます。 |
| バスレフ型 :ヘルムホルツの共鳴管の原理を利用し、キャビネット内の低音を外に取り出す方式です。最も一般的です。 | |
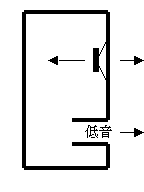
|
長所: 密閉型に比べ、空気バネ効果が小さく、生き生きと鳴ります。低音の豊かさも上です。キャビネットの大きさも、ある程度自由です。ダイナミック・レンジも密閉型よりあります。 短所: 共鳴管は共鳴周波数の周辺のみ強調するので、不自然な強調感のある低音になる事があります。また、共鳴周波数以下の低音に対しては、密閉型の方が有利です。 |
| ダブル・バスレフ型 :キャビネットを2つに分け、共鳴管を2つ取り付ける方式です。 | |
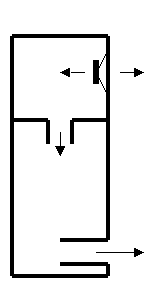
|
長所: ゆとりのある深い音が得られます。バスレフの強調感も緩和されます。2つの共鳴周波数をうまく利用すれば、かなり低い低音まで得られます。 短所: キャビネットが大きくなります。2つの共鳴管を鳴らすには、ある程度強力なユニットでないと良い効果が得られません。ダイナミック・レンジはバスレフより多少劣ります。 |
| バックロード・ホーン型 :ユニット後方に放射される低音をホーンにつなげて取り出す方式です。 | |
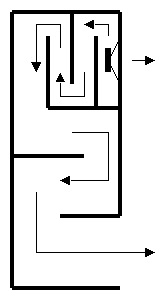
|
長所: ユニットの後ろから出る音の周囲に覆いをかぶせる(ホーンにつなげる)ことで、低音の空振りを防いでいます。 空気バネ効果が少なく、しかもユニット後方の音も殺さないので、最高のダイナミック・レンジです。微小な音も輪郭がぼやけません。フォルテッシモのピアノの音圧も正確に、圧倒的迫力で再現します。低音も50HZまでは、どの方式より優れた特性を示します。自作派が一度は必ず作ってみたいと思う型です。 短所: ホーンで十分な低音を取り出すには、2m以上の長さが必要で、キャビネットはかなり大きくなります。ホーンを通る分、低音は遅れて出てくるので、それが感じられる時もあります。また、長いホーンにもへこたれない、専用に設計されたユニットを使う必要もあります。 |
| ユニットの種類 | ||||||||
|
スピーカー・ユニットは面積が大きい程、そして重量が大きい程、低音再生に有利です。面積が大きくなれば空振りも減るし、重い程最低共振周波数が下がるからです。しかし、高音再生には不利になります。高い周波数で振動させるには軽く、小さいものほど有利だからです。つまり、万能なユニットはないのです。
メーカー製の3wayスピーカー等は、ネットワーク回路を組んで、それぞれのユニットに信号を分配しています。このネットワークによる音質劣化は無視しがたいものがあります。 特にダイナミックレンジは格段に狭くなります。 それに、ひとつの音が上中下3つの場所から出てくるので、音の輪郭があいまいになり、音場感も良くありません。 そこで、自作派はフルレンジタイプを良く使います。ネットワークがないので、生き生き鳴りますし、音場感も良いからです。私が初めて製作したスピーカーで人の声を再生してみた時は本当に驚きました。本当にそこに人がいるように聞こえるのです。「モニター100」では聞けなかった音でした。ただ、やはり、高音や低音には不満でした。高音の問題は、コンデンサーを挟んだだけのシンプルネットワークでツイーターを追加したら解決されました。フルレンジのすぐ上に配置したので音場感もあまり変わりません。問題は低音です。そこでバックロードを製作してみました。バックロードで出てくる低音は200hz以下なので、音場感も損なわれません(200hZ以下の音は人間の耳は方向を感知出来ません)。これでOK!音質もダイナミック・レンジも音場感も、「モニター100」を上回るものが出来たのです。 |
| 製作の手順 |
|
スピーカーはユニットだけが振動するべきものです。キャビネットが振動しないよう、丈夫に設計してください。補強材も積極的に用いましょう。 楽しい設計が終われば、後は板取りです。合板を使うのが一般的です。一般的な合板のサイズは「92cm×183cm」です。厚みは15mmから23mmまでが扱いやすいです。無駄のない板取りを心がけ、余れば棚などいかがでしょう。板はホームセンターで売っている「シナ合板」が良く使われます。剛性も強いし、表面は美しくかつ安価だからです。カットサービスしてもらえば、かなり製作は楽になります。  1枚の合板がこうなる。 板同士の接着には木工ボンドを使います。良く圧着すればかなりの強度になります。圧着するには釘で打ち付けるのが一般的ですが、小さければ重しを載せるなどすれば十分です。「ハタガネ」という器具があれば、少々大きくても釘なしで固定できます。中に吸音材を入れるのを忘れないようにしてください。吸音材はキャビネット内の空気の共鳴を押さえる働きがあります。密閉型は多く、バスレフは側面程度、バックロードは1枚入れる程度にしてください。  グラスウールを詰める。 接着したら、表面をヤスリがけし、ニスを塗ります。きれいですし、強度も上がるからです。乾燥したら、いよいよユニットを取りつけます。コードはハンダ付けがいいでしょう。ユニットを傷つけないよう保護しながらドライバーを回してください。  ニス塗り。 いよいよ視聴!え?あまり良い音じゃない?はいはい。わたしにも経験があります。製作したばかりの時は、箱もボンつくし、ユニットのエージングも進んでいないので、がっくりくるような音しか出てきません。箱、ユニットともに1週間も鳴らしこめば見違えるような音になります。  音だしの瞬間・・・。 |
| ロッカー永田自作スピーカー集 | |
| ここでは私ロッカー永田がこれまでに製作してきたスピーカーを紹介しましょう。 成功例もあれば失敗作もあります。 はっきり言えば、長岡先生の設計に忠実に製作した作品は失敗はあまりありません。 設計からすべて自分の手で行った作品には失敗作もあります・・・。 | |
| モアイ :バスレフ+スーパーウーハー | |

|
制作費:約12万円 ユニット:フォステクスFT96H+FE168Σ+FW168*2 長岡先生会心の傑作!最初は、後輩のプリティ金子の結婚祝に製作したが、あまりに素晴らしいので、自分用にもう1セット製作してしまった。FT96Hによるあくまで澄み切った高音。FE168Σらしい生々しいボーカル。FW168(2連発)による締まった低音。まさにモニタースピーカー。基本は16cmフルレンジFE168Σをダイレクトに鳴らし、ツイーター、ウーハーはあくまで補助。このスピーカーの音はほとんどFE168Σで決定されている。シャープで生々しい音だ。フィルターがかかってない音と言えば分かってもらえるだろうか。モアイの成功は、FE168Σという高性能フルレンジの良さを完璧に引き出した上に、さらにはスーパーツィーター、スーパーウーハーとのつながりも見事という点にあるだろう。私はこれを超える音を聴いたことがない(後日談:訂正します。長岡先生の箱舟にお邪魔したら、その音はやはりすごかった。)。モアイの音は長岡氏のメインシステム「箱舟」の音に似ている。それはそうだ。あちらは20センチフルレンジFE208Sを共鳴管で鳴らし、スーパーツィーター、スーパーウーハーで補助するというシステムだから。モアイはその弟分に当たると言える。6畳で「箱舟」の音が聴ける素晴らしいシステムがモアイなのである。上下分割タイプでセッティングの自由度も高い。ラックも自作。 |
| 16cmフルレンジ・大型バスレフ | |

|
制作費:約6万円 使用ユニット:フォステクスFE168Σ+FT96H(ツイーター)
|
| 16cmフルレンジ・バックロードホーン | |

|
制作費:約二万5千円 使用ユニット:テクニクス16F20 初めて作ったバックロード。友人の外園に手伝ってもらい、2日がかりで製作。かなり大変だったが、音を出してみて、すごくがっかり。箱はボンボン鳴るし、変な共鳴音がまとわりつく。ところが、2日たって鳴らしてみたら大変身。音はクリアになり、朗々と鳴る。驚いたのは、ピアノ。本当にそこで誰かが弾いているよう。この生々しさは、ダイナミックレンジが広いおかげだろう。バックロードならではの音。あくまで忠実に音量を再現していた。音質ではモアイが勝っているが、この点では、こちらが上。これでバックロード特有の共鳴音や低音の暴れを押さえることが出来れば素晴らしいシステムになるだろう。ただ16F20はメリハリは良いのだが、しなやかさや音の艶はあまり出さないようだ。今ならFE168SSがある(FE168Σはバックロード向きではない)。このシステムは妻の妹にもらわれていった。ピアノの練習にちょうど良いだろう。 |
| TV用3Dシステム | |
 
|
制作費:約1万5千円 使用ユニット:フォステクス FE87+テクニクス14F11 中高音用サテライト(バスレフ)+スーパーウーハーという構成。200HZ以下の低音をスーパーウーハーで再生。200HZ以下は方向感がないので、部屋の隅に設置。低音が出過ぎるため、アンプのトーンコントロールで低音を絞っている。スーパーウーハー部は完全に失敗。やはりウーハーを使うべきだった。サテライトは成功。というか、サテライトに使用したユニットFE87(8センチフルレンジ)はFE83、10センチフルレンジのFE103やFE107と共に自作派永遠の友と言われており、密閉、バスレフ、バックロードなど何に用いてもそれらしく鳴ることで有名である。FE87サテライトはFE87の良さがわかる、小気味いい音。TV用なので防磁タイプのFE87を使用したが、そうでないなら非防磁タイプのFE83を使用したほうがクリアな音質になるだろう。 |
| パソコン用8cmバックロード | |
 
|
制作費:約1万二千円 使用ユニット:フォステクス FE87 パソコンでもしっかりした音が聞きたくなり、設計してみた。ホーン長が1.5mしか取れないので、不安だったが、製作したら100HZまでは十分再生した。やはり製作した当初はしょぼい音しか出さなかったが、2日程で変身した。今でも小気味よく鳴ってくれている。同サイズのダブル・バスレフも製作したが、バックロードの方が迫力があった。一方、ダブル・バスレフは繊細な音を出していたので、父のパソコン用にプレゼントした。どちらも製作しやすく、お薦め。ちなみにパソコンも自作。 |
| フラミンゴⅡ :8cmバックロード | |

|
制作費:約2万円 使用ユニット:フォステクス FE83 設計は長岡鉄男のフラミンゴを参考にしたが、かなり変更してある。長岡版では小型にするため、バックロードホーンのひろがり率を抑え目に取っているが、永田版では、スーパースワンと同じひろがり率を確保している。ユニットの後ろには鉛のインゴットを付けて、余計な振動を押さえた。またフレームには鳴き止めの為ブチルゴムを貼った。この対策で音質はクリアになったと思う。この作品のメリットは、なんと言っても、理想的な点音源スピーカーだという点だろう。何を聞いても、目の前に音像がピシッと定位する。実に心地よい。これは他のどんなスピーカーより優れている。また、フルレンジ一発使用のバックロードなので微小信号にも強く、小音量時の繊細な音は素晴らしい。ただ、FE83は、もともとバックロードに向くほど磁気回路が強力ではないので、その点がデメリットとなってしまっている。低音に締まりがないのだ。気になるほどではないが。「モアイ」を90点とすると、この作品は75点くらいである。オカルト岡本にプレゼントした。 |
| オゾン1号2号 :16センチダブルバスレフ | |
 
|
制作費:約3万円 使用ユニット:フォステクス FE167+FT17H ユニットが余ってたので作ってみた。 第一容積23リットル、第1fd=130HZ、全容積53リットル、第2fd=60HZ、バスレフ開口面積は、低音を稼ぐためどちらも100平方センチと多めに取った。 音は意外とクールでモニター調。ダブルバスレフ方式により低音はかなり伸びてはいるが、ふくらみ感には欠ける。細身のすっきりとした上品な音だ。 内容積が大きいので、ゆとりのある響きが聞ける。FE167は防磁タイプのAV用ユニット。もともと切れ込むタイプではなく、おとなしく控えめな音である。 磁石はあまり強力ではないので、ダンプ不足から低音がブーミーになる不安もあったが、意外や意外、締ったクールな音だった。割と強力なのかもしれない。 音質はFE164の方が良いだろうし、さらにFE168Σに変えれば、かなりのパフォーマンスを示すだろう。16センチフルレンジは種類も豊富だ。 様々なユニットが候補になる。おぞん野村の新婚家庭にプレゼント。ちなみに左チャンネルが1号、右チャンネルが2号。 分けたのは二人が離婚した場合のトラブルを考慮してのことだ。もちろん、冗談である。 |
| カースピーカーその1 :8センチバスレフ | |

|
制作費:約1万円 使用ユニット:フォステクス FE83 車で音楽を聴く場合、ほとんど反射音で聴くことになるのが我慢できなかったので製作したのがこれ。 私の車に乗った人がことごとく驚いてくれるスピーカー。その度ににやにやしながら説明する。 水道管の塩ビパイプ部品を買ってきて、プラモデル感覚で製作。楽しかった。 車のカーブにあわせてパイプを曲げるのが難しかった。ガスコンロであぶってなんとか調節。 うまいことバスレフポートになりそうな3つ股パイプを見つけたときは狂喜した。 音はそれなり。もちろん低音は駄目だが、直接耳に届くのがうれしい。ただドライバーにしか良さが分からないのが難点。 |
| カースピーカーその2 | |

|
制作費:約0円 使用ユニット:日立のラジカセパディスコW1のユニット リアスピーカーとして中学のころ愛用していたラジカセからユニットをはずして付けてみた。 かなり良い音がしていたが、すでにオシャカ。 合掌。 |
| センタースピーカー内蔵AVラック | |


|
制作費:約3万円 使用ユニット:FOSTEX FE87 5.1ch化を目論み、考えに考えた末にこの形になった。 ごちゃごちゃしていたAV関係がすっきりとまとまった。 なかなか良くできたとめずらしく自画自賛している。 センタースピーカーってAVの定位にはとても重要だと分かった。 人の声がしっかりと真中から聞こえるのは疲れないのだ。 |
| 長岡鉄男追悼企画スーパースワミンゴ3部作 | |




|
制作費:約8万円 使用ユニット:FOSTEX FE167, FE88ES, FE108ES 製作期間:2001年3月~4月の2ヶ月間 長岡鉄男氏の逝去をきっかけに取り組んだ大作。 長岡鉄男氏の代表作、スーパースワンとスーパーフラミンゴを合体させた夢のスピーカー。 基本はスーパースワンだが、 ヘッドを交換することにより、 スーパーフラミンゴに変身したりする。よってスーパースワミンゴと命名。 FE167が余っていたので、ついでにそれも製作。 1台で3台分楽しめる愉快な作品となった。 音の傾向は以下の通り。 FE88ES: ユニットの素性の良さを反映して、極めて繊細な音。低音も十分出る。 若干中音部にホーンの残響のような響きが乗るところが残念。 これさえなければ素晴らしい高級スピーカーになるだろう。 いやいやFE88ESは素晴らしいユニットだ。 いつか使いこなしたい・・・。 FE108ES: 最もバランスの良い音。 ユニットの特性かシャープな音だ。 一聴してハッとさせるものを持っているが、 長く聴くと疲れる。 色気は88ESの方が優れている。 低音はモリモリ出る、というか4畳半の部屋なので出過ぎる。 とにかく迫力があり、もっと大きな部屋で使いこなしたい。 FE167: 他の2つとは違って、磁力も弱いしローコストなので、 音そのもののクオリティは一番低い。 しかし、やはり16センチ、余裕を感じさせる。 無理なく朗々と鳴っている。 ホーンとのつながりも意外にスムーズな様子。 聴いていて一番疲れない。自然だ。 |
ぜひ皆さんも! |